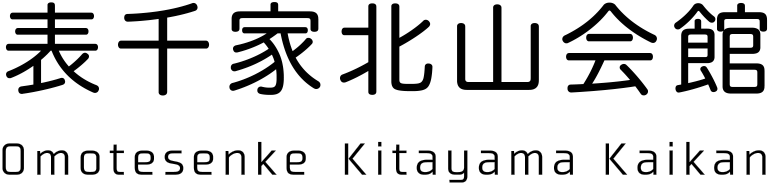これまでの催し
第14回 茶の湯文化にふれる市民講座
テーマ「茶の湯の釜と金工」
大西家の歴代が伝統的な技術や精進を重ねて造りあげられた作品を展示する特別展にあわせて、テーマを「茶の湯の釜と金工」といたしました。茶会記にみえる釜とその他の道具との関わりについて、芦屋釜や天明釜の歴史的な展開と京釜のこと、茶事における釜の存在とその魅力、そして作り手の立場からみた釜の見方など、4人の講師をお招きして、いろいろな角度から幅広く茶の湯釜の世界を探求しようと企画いたしました。
2009年11月21日(土)
「茶の湯釜の歴史
―芦屋釜、天明釜から京釜へ―」

原田 一敏 氏
(東京国立博物館 上席研究員)
鎌倉時代に喫茶の風が広まり、茶の湯の道具が整えられてきますが、喫茶専用の釜が用いられるようになるのは南北朝時代ころからのことです。その代表的なものが芦屋釜でした。室町中期まで畿内において武家、公家、寺院の間では釜といえば芦屋といわれるほど賞用されました。しかし室町時代後期になると芦屋釜に変って天明釜が多く用いられてきます。それは当時の茶会記からも窺われます。しかし、千利休が活躍するようになると地元である京の三条釜座の釜師に形を示して注文、あるいは直接釜座に赴いて求めるという直接釜の創造選択へと変って行くようになりました。
| 主催 | 表千家北山会館、京都新聞社 |
|---|---|
| 後援 | 京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局 |