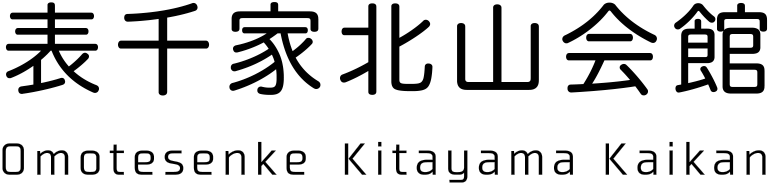これまでの催し
第14回 茶の湯文化にふれる市民講座
テーマ「茶の湯の釜と金工」
大西家の歴代が伝統的な技術や精進を重ねて造りあげられた作品を展示する特別展にあわせて、テーマを「茶の湯の釜と金工」といたしました。茶会記にみえる釜とその他の道具との関わりについて、芦屋釜や天明釜の歴史的な展開と京釜のこと、茶事における釜の存在とその魅力、そして作り手の立場からみた釜の見方など、4人の講師をお招きして、いろいろな角度から幅広く茶の湯釜の世界を探求しようと企画いたしました。
2009年12月5日(土)
「茶の湯釜の歴史と鑑賞」

大西 清右衛門 氏
(千家十職 釜師)
大西家は約400年にわたり京都・三条釜座にて茶の湯釜を作り続けてきました。6代浄元の頃より千家出入りの職家として、また中世「釜座」の伝統を継承する唯一の家として、現在に至ります。釜は、茶の湯において一室の主人公というべき存在でありながら、そのたのしみ方においては、近年あまり意識されてこなかった道具かもしれません。いずれは朽ち果てる鉄という素材を用いながら、創造性に満ちた造形や精緻な技を極め、「朽ち」や「荒れ」など侘びを象徴する美意識に裏打ちされた、見どころ豊かな茶の湯釜の世界。今回はその魅力を、作り手の立場からお話しいただきました。
| 主催 | 表千家北山会館、京都新聞社 |
|---|---|
| 後援 | 京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局 |