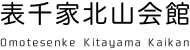第11回 茶の湯文化にふれる市民講座
 西田 宏子 氏
西田 宏子 氏
根津美術館 次長
テーマ「九州古陶磁の魅力」
九州は大陸文化を受け入れる日本の玄関でした。大陸の進んだ陶磁の技術もその一つで、九州陶磁は16世紀以来、美濃、瀬戸にさきがけて多様な発展をとげ、日本陶磁の中で重要な位置を占めるに至ります。今日でも、九州各地で造られる日常の食器として、あるいは美術工芸品としての陶磁器に対する関心は国の内外を問わず、ますます盛んなものがあります。
田中丸コレクション所蔵の九州古陶磁名品展にあわせて当代一流の陶磁研究者の方々に九州陶磁の世界をより深く取り上げていただきました。
2006年11月25日(土)
「二彩唐津から高取そして仁清へ」
西田 宏子 氏(根津美術館 次長)
唐津焼のなかでも特殊な作行きをみせる二彩唐津と言われる作品があります。これは江戸時代前期に日本全国を市場として、大いに流行した陶器でした。その白土を化粧し、これに緑、黄、茶などの色釉を大胆に掛け分ける技法は、やがて高取焼にも影響を与え、さらに京都の仁清にもその影響を見る事ができます。
茶陶になりにくい二彩唐津ですが、その施釉方法が茶の湯の道具として好まれたのでしょう。今回は、その展開を語っていただきました。
 西田 宏子 氏
西田 宏子 氏根津美術館 次長
| 主催 | 表千家北山会館、財団法人田中丸コレクション、京都新聞社 |
|---|---|
| 後援 | 京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局 |
| 協力 | 九州国立博物館、福岡市美術館、佐賀県立九州陶磁文化館 |