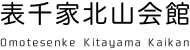第11回 茶の湯文化にふれる市民講座
 林屋 晴三 氏
林屋 晴三 氏
東京国立博物館 名誉館員
テーマ「九州古陶磁の魅力」
九州は大陸文化を受け入れる日本の玄関でした。大陸の進んだ陶磁の技術もその一つで、九州陶磁は16世紀以来、美濃、瀬戸にさきがけて多様な発展をとげ、日本陶磁の中で重要な位置を占めるに至ります。今日でも、九州各地で造られる日常の食器として、あるいは美術工芸品としての陶磁器に対する関心は国の内外を問わず、ますます盛んなものがあります。
田中丸コレクション所蔵の九州古陶磁名品展にあわせて当代一流の陶磁研究者の方々に九州陶磁の世界をより深く取り上げていただきました。
2006年12月9日(土)
「九州古陶磁にみる茶陶の魅力」
林屋 晴三 氏(東京国立博物館 名誉館員)
桃山時代、天正年間から江戸時代初期 慶長・元和・寛永年間にかけて、日本の茶陶は空前の盛況をみせた。侘数寄の茶の湯の拡がりが京都の長次郎をはじめ、瀬戸、美濃や信楽、伊賀、丹波、備前などの古窯における茶陶の生産をうながした。さらに、天正年間後期から唐津焼の茶陶、文禄・慶長の役後の唐津、上野、高取、薩摩、萩などの窯業地における陶窯の興隆にともない、それぞれに茶陶を焼造した。それらのなかから優れた作品を捉えて、スライドによってその美と特質を解説された。
 林屋 晴三 氏
林屋 晴三 氏東京国立博物館 名誉館員
| 主催 | 表千家北山会館、財団法人田中丸コレクション、京都新聞社 |
|---|---|
| 後援 | 京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、NHK京都放送局 |
| 協力 | 九州国立博物館、福岡市美術館、佐賀県立九州陶磁文化館 |