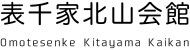特別展の主題「表千家歴代ゆかりの茶碗、服紗」にもとづき、2回の講座が開催されました。
2023年10月29日(日)
「茶の湯の語り部 写し物」
松本 英樹 氏(家元教授、表千家同門会理事)
松本氏は、「写し物」が何故作られるようになったのか、「写し物」がお茶の世界で果たしてきた役割について集められた資料を用いてお話をされた。
氏はまず抹茶の基本的な解説として茶の伝来の歴史をお話され、中国で発祥した抹茶が宋の禅院でどのようにお茶が飲まれていたのかを大徳寺に伝わる「五百羅漢図」や建仁寺の四ツ頭茶礼を例にお話された。
「抹茶」の喫茶法が日本に伝来した際に、お茶を点て飲むための道具も同時に伝わり、抹茶が普及して使用する道具は目的に応じた国産の代用品が作られ使われた。しかし「茶碗」と「茶入」だけは中国産と同形の「写し物」が作られその理由としては、茶碗は台にのせて点てる代用品が日本になかったこと。茶入は有名な唐物茶入と同じ物が欲しいと思う人が増える中で、日本において同じ形の物、つまり「写し物」が作られるようになる。それは当時高価な輸入品が日本で作られるという画期的なことであった。
茶の道具に「写し物」が増えるのは利休以降の時代である。それは利休の侘茶にかなった茶碗などの新たな道具を考案するなかで多くの人が、利休の侘茶に憧れたからである。利休の時代は、茶碗がいろいろと形を変えた時代でもあると話された。
今日においても茶碗の大きさは変化しているが、利休形に似たものが多い。それはかつて利休の茶をまねたいと考えた人が利休が所持する道具と同じ形の道具を欲したように、利休の茶を継承するには、利休がみとめた道具を使うのが良い方法であり「利休形」の写し物が用いられる様になる。
「写し物」が作られる理由は様々である。お茶を学ぶ人にとって家元の道具を写すということが単にものをコピーするということではなく、席主の茶での使い方次第で、「写し物」も主役になりますという言葉をもって、講座を締めくくられた。
 松本 英樹 氏
松本 英樹 氏