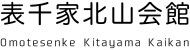第22回 茶の湯文化にふれる市民講座
 貫名 義隆 氏
貫名 義隆 氏
家元教授
表千家同門会 理事
特別展の主題「表千家歴代ゆかりの茶入、茶器、茶杓」にもとづき、3回の講座が開催されました。
2017年11月23日(木・祝)
「茶入、茶器、茶杓からみる感性と表現」
貫名 義隆 氏(家元教授 表千家同門会 理事)
天正15年6月、66歳の利休は、秀吉に従って博多に滞在し、14日箱崎灯籠堂に神屋宗湛らを招き茶会を催します。高麗筒の花入、備前の肩衝き茶入、折撓(おりため)の茶杓などが『宗湛日記』に記されています。
特に茶入については、利休が「此茶入ハホテイト申候、袋ハカリナホトニト有也」と述べたとあります。茶入に銘をつけ、一会の中で主客が感覚を共有する。茶入、茶杓には特にその趣が強く表現されるように思われます。縄文、弥生から伏流水のように続く日本美の流れが、茶の湯に如何に表現され取り合されるかについて、茶入、茶器、茶杓を中心としてお話しいただきました。
 貫名 義隆 氏
貫名 義隆 氏家元教授
表千家同門会 理事
| 主催 | 表千家北山会館、京都新聞 |
|---|---|
| 後援 | 京都府、京都市、京都府教育委員会、京都市教育委員会、京都市内博物館施設連絡協議会 |