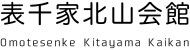特別展
 熊倉 功夫 氏
熊倉 功夫 氏
2024年11月3日(日・祝)
「茶の湯の趣向と心」
熊倉 功夫 氏(MIHO MUSEUM 館長)
茶会を開こうとすれば、誰しもが心を悩ますのが趣向である。どんなテーマで、それをどのように表現するか。その悩みが茶人の苦しみでもあり、何よりの楽しみである。
茶会記が残されるようになった十六世紀後半の茶会では名物道具が趣向の第一であった。名物を持つ亭主であれば、名物を出し、客はそれを拝見して満足する。さらに名物を出すだけでなく、その使い方や拝見の仕方も趣向の一つになった。
名物道具を持たないわび茶人は、アッと人を驚かせるような茶会の演出を試みる。思いがけぬ仕掛をたくらんで、わざと客を困らせたりもした。しかし江戸時代に入って茶の湯が落着いてくると、やりすぎた演出は評価されなくなる。茶の湯が日々の生活の中に溶けこんできたからであろう。心と心が交わる淡々とした境地が求められるようになった。しかし今も二つの茶の湯の伝統は生きているのではないだろうか。その歴史をたどってみたい。
 熊倉 功夫 氏
熊倉 功夫 氏オンラインギャラリートーク
北村美術館四君子苑特別見学
茶の湯文化にふれる市民講座
- 2024年10月19日(土) 「わびと数寄―松平不昧を中心に―」
木下 收 氏(北村美術館館長) - 2024年11月30日(土) 「わびと数寄―近代数寄者・松永耳庵を中心に―」
木下 收 氏(北村美術館館長)